§7-3 太陽光発電を普及させるためには
1. 太陽光発電の役割
環境問題の中で、地球温暖化対策を市民の立場から何ができるのでしょうか。温暖化ガスを発生しないエネルギー源として、太陽光および太陽熱を活用する機器を住宅に設置する政策は、1974年の石油危機以来、政府が機器の開発に補助金を出して推進してきた政策です。このエネルギー対策において、太陽熱の方が先行して全国の家庭でかなり普及しましたが、90年代あたりから減少傾向にあります。原油価格が歴史的に低下したため家庭は太陽熱より電気・ガスを直接使っていたのだと推測されます。太陽光の場合は、90年代半導体の使用が飛躍的に増加し、太陽光のセルを製造するコストが下がったため、家庭が住宅に設置するコストが下がりました。同時に、国の「ニューサンシャイン計画」により、太陽光・太陽熱機器に補助金が給付されることになり、90年代から徐々に設置件数が増加していきました。
フロンガスのオゾン層破壊を防止する国際取り決めが成立して以来、地球温暖化対策は、次の課題として議論され、1997年京都議定書として取りまとめられました。条約が発効すれば、炭酸ガス発生量に目標値が設定され、それを達成する義務が生じます。日本は、2008年から2012年まで、1990年の排出量より6%減少させる義務を負っています。他方、2000年代に入りやはり年平均気温は上昇していますし、気候変動が自然災害を多発させ、温暖化傾向は確かになってきました。京都議定書の次の条約をめぐって、毎年、国際会議が開かれていますが、米国と中国を引き込み、新興国に義務を負わせることに失敗しています。
地球温暖化問題は、いろいろの立場から考えることができる、学際的および市民的課題です。この問題に対して、現在、日本は京都議定書の義務を達成することに対して努力しています。さらに、民主党政権は、2020年までに1990年の排出量より25%削減を達成することを国際公約しました。したがって、日本の家計部門では、長い時間をかけて、日本のエネルギー政策の原点である太陽光および太陽熱を活用する機器を住宅に設置する政策を強化せざるをえなくなりました。
経済学の立場から、各家計が太陽光発電設備を設置することと炭酸ガス排出量を25%削減する国家目標との関係を説明します。経済学では、太陽光発電設備を生産し、販売するのは、企業であり、購入するのは、家計です。企業の生産能力は年々増加していますが、購入する家計は販売価格が1kWあたり50万円ですから、携帯電話のように急速に普及はしません。政府には、炭酸ガス排出量を削減する義務がありますから、普及率を上げるため、購入に補助金を給付してきました。経済学では、購入側の需要と販売側の供給の法則により、太陽光発電設備の価格が決まりますが、政府の補助金があるため、購入者はその分安く購入できます。補助金は税金から支出され、国民が負担します。これらの関係を以下でより詳しく説明します。
2. 太陽光発電設備を設置するには
太陽光機器を製造する企業は、国の補助金制度で、研究開発費を補助してもらい、発電効率を15%から20%以上に上げるよう研究しています。しかし、製品価格184万円は家計にとっては、自動車を買う価格であり、しかも、持ち家がなければ、設置が困難です。太陽光機器の設置は、政府の削減目標を達成する手段であり、家計が実行できることですが、高価であるため、液晶テレビなどの家電を買うようには、普及しそうにありません。
そこで、政府は太陽光発電設備の普及を促進するために、2006年以前では、太陽光発電設備を設置すると、国から1kWについて4万円、地方自治体でも4万円以下の補助金が出ていました。また関西電力が太陽光発電の余剰発電量を1kWhあたり24円で買取る制度がありました。工事費や、配電機器を含んだ設置費用は、1kWあたり50万円でした。現在も、3kWまでは同じで、4kW 以上ではいくぶん安くなるようです。4kWを設置すると200万円かかり、地方自治体の補助金制度を使えば、200万円-16万円=184万円で設置できます。
私は、西村ゼミ演習Iの学生とともに、茨木市において、普及の現状と可能性を調べ、家計部門の太陽光発電量を推計してきました。2004年から2006年まで、実際に、学生と茨木市内の各住宅を回って、太陽光発電設備を設置している住宅を調べると、普及率は約1%でした。設置すると発電効率が高い南方向に建築されていない、屋根の形が複雑で面積も小さい住宅は除いて、設置補助金が国や自治体から出る、3kWの太陽光発電設備が設置可能な住宅を調べると約62%でした。新築の住宅の場合、南向きと屋根の形を配慮して発電効率のもっともよい設計をすれば、補助金や減税措置で、費用が軽減されて普及率は上昇するでしょう。新築や建替はそれほど毎年増加しませんから、国の対策としては、62%の既存の住宅に設置してもらうことが、当面の課題であることがわかります。
3. 太陽光エネルギーのCO2削減量
太陽光エネルギーは再生可能エネルギーであり、炭酸ガスを発生しませんから、化石燃料で発電された電気を削減する効果があります。太陽光発電量を石油に換算する方法とそれをCO2削減量に換算する方法は、それぞれ、『NEDO導入ガイドブック』1998年3月と『太陽光発電評価の調査研究』1997年3月によると次のとおりです。
3kWの太陽光発電量は、関西地方では、年間3,000kWhと推定されます。1kWの太陽光パネルで年間1,000kWhです。
推定発電量 3,000kWh 石油削減量 729ℓ/年 CO2削減量 533.9kg-C/年
石油削減量の算出条件は、
石油熱量換算: 9,250kcal/ℓ
発電に必要なエネルギー: 2,250kcal/kWh
必要な石油量: 2,250÷9,250=0.243ℓ/kWh
です。3,000kWhであれば、0.243☓3,000=729ℓです。
CO2削減量については、金山公夫・馬場 弘『ソーラーエネルギー利用技術』p251 に、エネルギー種別発熱量あたりCO2排出係数が、表1のように示されています。
CO2削減量= 発熱量×CO2排出係数
から、CO2削減量=(2,250kcal/kWh)×3,000 kWh☓79.1(A重油) ÷ 1,000,000kg-C/kcal
=533.9 kg-C
です。
表1 エネルギー別発熱量あたりCO2排出係数
|
エネルギー種別 |
|
発熱量あたりCO2 |
エネルギー種別 |
|
発熱量あたりCO2 |
|
|||||||
|
|
|
|
排出係数kg-C/Gcal |
|
|
|
排出係数kg-C/Gcal |
||||||
|
ガソリン |
|
|
76.6 |
|
B・C重油 |
|
|
81.1 |
|
||||
|
灯油 |
|
|
77.5 |
|
LPG |
|
|
68.3 |
|
||||
|
軽油 |
|
|
78.4 |
|
電力 |
|
|
152.4 |
|
||||
|
A重油 |
|
|
79.1 |
|
都市ガス |
|
|
58.4 |
|
||||
1Gcal=1,000,000kcal=1,000Mcal,G:ギガ=10億,M:メガ=100万
出所:金山公夫・馬場 弘『ソーラーエネルギー利用技術』森北出版,2004年,p251.
4. 政府の家計部門に対する削減目標と太陽光普及政策
政府の京都議定書目標達成計画では、2010年度、家計部門は、炭酸ガス排出量を138~141百万t-Cが目標ですが、2006年度で、166百万t-Cであり、基準年度が127百万t-Cですから、30%増加しています。少なくとも25百万t-Cを削減する必要があります。そのためには、1住宅4kWのパネルで、年間(2,250kcal/kWh)×4,000 kWh☓79.1(A重油)÷ 1,000,000kg-C/kcal=0.712t-C削減できますから、日本の住宅1千万軒に普及させれば、7.12百万t-C削減できます。つまり、日本の住宅1千万軒の太陽光発電で、25百万t-C の35%は、削減可能です。
国の補助金制度は、2006年7月に終わりました。地方自治体の補助金制度は、国の補助金制度を補完する制度でしたが、大阪府の各自治体では、補助金制度が残っています。
国の買取制度は、2009年度11月から始まった新しい制度です。その仕組みは、次のとおりです。太陽光発電設備で発電された電力のうち、使わなかった電力は、電力会社が国の定める条件で買い取る制度です。買い取られた費用は、電気を使用している使用者すべてが、電気使用量に応じて、「太陽光発電促進賦課金」として負担することになっています。
買取価格(住宅用)
10kW未満 48円/kWh
買取価格および「太陽光発電促進賦課金」は、国の審議会で毎年決めます。買取開始年度の価格が10年間適用されます。「太陽光発電促進賦課金」は2011年3月分まで0銭/kWhで負担は生じていません。電気使用者が全員で、太陽光発電促進をする使用者が増加するのを支えていこうということです。2006年度までの制度と比較すると、国の税金は投入されません。太陽光発電協会の統計資料を見ますと、国の補助金制度が終了すると住宅用の太陽電池出荷量が減少していますが、2009年度から急激な増加に転じています。太陽光発電者はこの買取制度で、10年で設置費用を回収できる見込みであり、太陽光パネルは、耐用年数が10年以上ということです。この設備を設置できない使用者は、直接的に炭酸ガス削減負担金を設置者に支払っていることになります。経済学的に見て、この制度は持続性があるのか、非常に興味ある問題を含んでいます。
図 1 日本における太陽電池出荷量の推移
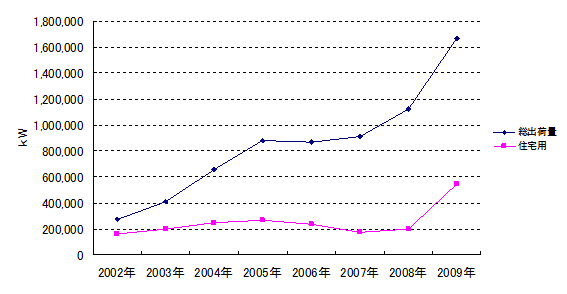
出所 太陽光発電協会 http://www.jpea.gr.jp/より作成。
10『環境経済評価』プロジェクト
ホームへ